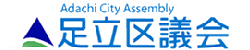
11 1,000名以上の死亡被害を出している新型コロナワクチンの潜在的な被害救済のため、足立区民の死亡者の接種歴データと死亡届データを照合したデータ公開を求める陳情
令和7年10月2日
【陳情の趣旨】
新型コロナワクチン接種後の健康被害は過去に類を見ないほど甚大である。過去の薬害は多くて10,000人規模の被害であるが、新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済制度の認定件数は9,310件(うち死亡認定1,038件)となっており現在も被害認定が増え続けている。様々な報道や開示請求資料等を確認すると、現在表に出ている薬害級の数字は氷山の一角であることが明らかになってきている。予防接種法第3条「予防接種に関する基本的な計画」にある自治体の役割「適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び住民への情報提供等を行う」に則し、接種歴と死亡データを照合したデータを公開することで接種直後の死亡事例等を洗い出し、表に出てこない潜在的な被害者の救済を進めることが出来るはずである。
接種が開始された2021年2月以降の足立区民の死亡者の新型コロナワクチン接種歴データ(接種回数、接種日、ワクチンの種類、ワクチンのロット番号)と死亡届データ(死亡日、年齢、性別、死因速報値)を照合し、そのデータ公開を求める。
【陳情の理由】
1.現在も続く異常な死亡者増加と新型コロナ対策総括の必要性
2021年春頃より日本全体の死亡数が激増している。厚生労働省の人口動態統計によると、2021年は前年比約6万7千人増、2022年は約12万9千人増となっている(例年は2万人前後の増加幅)。それまで戦後最多であった東日本大震災時の約5万6千人をはるかに超える異常な増加数となっている。足立区においても全国と同様の傾向が見られ、2021年は643人増、2022年は710人増と例年(200人前後)より大幅な増加数となっている。
国立感染症研究所の発表では、新型コロナ以外の超過死亡数(実際の死亡数と予測される死亡数の差)は、2021年4月から2023年3月までの2年間で144,033人となっている。高齢化も踏まえた上での予測死亡数であるので、新型コロナや高齢化では説明できない大量の死亡者が現実に存在していることになる。加藤厚生労働大臣(当時)の参議院予算委員会答弁(2023年3月13日)や松野官房長官(当時)の記者会見(2023年4月6日)でも「超過死亡の原因は明らかでない」「原因を特定することは困難」と不明のまま放置されている状況である。
最近では新型コロナウイルス感染症対策分科会長を務めた尾身茂氏があるテレビ番組で「(新型コロナワクチンの)感染防止効果はあまりなかった」との発言が話題になったが、国・自治体・民間企業等様々な階層で新型コロナ対策の総括が必要なのではないか。マスク・アクリル板・自粛・ワクチン等様々な新型コロナ対策は果たしてどこまで有効だったのか。新型コロナワクチンは定期接種化され接種体制の整備は今後も続く自治体の仕事であるので、本来自己負担になる分の費用を自治体が補助するかどうかの是非含めて、予算編成の上でもワクチンの検証は必要なことではないか。
2.増え続ける新型コロナワクチンの甚大な被害
新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済制度の死亡認定は4桁をこえてしまい1,038名にのぼる(2025年9月30日最新)。新型コロナ以外の過去のすべてのワクチンの死亡認定151件(約45年間)の6倍以上の被害である。足立区においては新型コロナで初の死亡認定者が出てしまっている。救済制度の認定事例は判例と同様の蓋然性が必要であり(逐条解説予防接種法)、1種類のワクチンによる死亡の判例が1,000件を超えて積み上がっているともいえる異常事態である。
また副反応疑い報告制度の死亡報告は2,294名となり、そのうちの99%は情報不足のため評価不能のまま放置されている。これらの数字は厚生労働省のホームページに散り散りになっている情報をかき集めてはじめてまとまった形になるのであり、国民がワクチンの様々なリスクについて情報を収集するのは大変苦労する状況である。コロナ禍においてワクチンのメリットはメディア等で喧伝されてきたがリスクについては積極的に広報されたといえず、一国民としては情報開示請求等を活用でもしないと、接種を公平に判断する材料を見つけられないのが現状である。
また新型コロナワクチンはロット番号によって被害がかなり違うこともワクチン接種を慎重に考えている専門家により訴えられており、その内容は国会質問等でも取り上げられている(2024年12月17日参議院予算委員会川田龍平議員質問)。今回の陳情で求めるデータを開示すればロット差の問題や接種群と非接種群との比較等ワクチンのメリット・デメリットを考察することができるので、データ作成に協力的でない対応は国民の知る権利を阻害することになるのではないか。散々喧伝されてきた製薬企業の治験結果ではなく、陳情で求めるデータを公開することでわかる実際の足立区民の接種後のデータは、足立区民がワクチンを接種するかどうか、どう評価するかの一番の判断材料になるのではないか。
3.新型コロナワクチン接種歴と死亡届データを照合することで果たす自治体の役割
(1)副反応疑い報告制度の周知と薬害再発防止
厚生労働大臣記者会見で公表された予防接種健康被害救済制度と副反応疑い報告制度の突合結果(※1)や情報開示請求資料による浜松市の事例(※2)陳情者調べによる足立区の現状(※3)を見れば、副反応疑い報告制度が正常に機能していない、周知が徹底されていないことが明白である。その現状は厚生労働省から複数回周知依頼の通達が行われていることからもわかる。接種歴と死亡届データを照合すれば接種から死亡までの間隔がわかるようになるので、極端に間隔が短い事例は全例調査した上で改めて疑い報告をあげる等の施策をとることが出来る。予防接種法第3条「予防接種に関する基本的な計画」の「予防接種の安全性の向上のための副反応報告制度の円滑な運用」という役割を果たすことができるのではないか。副作用(副反応)の情報収集はサリドマイド事件の頃から重要な教訓の一つとされてきて、様々な薬害を経てついに法定化(2013年)されたのが副反応疑い報告制度である。薬害再発防止の根幹となる制度が機能していない状況でデータ作成に非協力的で放置している対応は、薬害発見を滞らせる・遅らせるような行為と受け取られかねないのではないか。
(※1)予防接種健康被害救済制度死亡事例の認定件数1,032件中、副反応疑い報告制度に提出されているのは306件(2025年9月5日厚生労働大臣記者会見より)。前述のように健康被害認定事例は判例同様の蓋然性が必要であるにもかかわらず、その死亡事例でさえも医者はワクチンとの関連性を3割程度しか認知していないことを示している。
(※2)静岡県浜松市の新型コロナワクチン接種後当日の死亡は9名、翌日の死亡は46名。そのうち副反応疑い報告に上がっているのはそれぞれ2名ずつのみ。当日・翌日の死亡でさえ疑いを持たず報告を上げない医師の認知不足がうかがえる。(浜松市情報開示請求資料より)
(※3)足立区の予防接種健康被害救済制度認定28件中、副反応疑い報告制度に報告されているものは4件。足立区においても報告を上げない医師の認知不足、自治体の周知不足がうかがえる。(足立区情報開示請求資料より)
(2)予防接種健康被害救済制度の周知と潜在的な被害の救済
上記同様に接種と死亡の間隔が極端に短い事例の中で、どのくらい予防接種健康被害救済制度を活用しているか調査することも有効である。救済制度の死亡認定数1,038件のうち268件は、疾病名・障害名の項目に「突然死」と記載されているからだ。判例同様の高い蓋然性のある認定事例において、接種後突然亡くなることは珍しいことではない。救済申請していない遺族に対し制度の周知を試みることで、被害に苦しむ遺族の救済ができるのではないか。国が被害救済に対し追加予算を110倍に増やし想定外の被害が出ている中、前述の医者の認知不足やPMDAの認知度調査結果のように周知不足が露呈している状況では、潜在的な被害者が数多くいることが予想される。住民や医者へ周知徹底して表に出てきていない被害者を掘り起こすことで、予防接種法第3条「予防接種に関する基本的な計画」の「適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済」という役割を果たすことができるのではないか。
(3)ワクチンの有効性・有害性の検証
接種歴と死亡届データを照合すれば、接種群と非接種群の死亡者の割合がわかるようになる。足立区議会厚生委員会での衛生部長答弁にあるようにワクチンが多くの命を救ってきたのであれば(※4)、ワクチンを打ってない非接種群の死亡が多くなることが予想できる。照合データを公開することで一国民としてはワクチン接種の判断材料になるとともに、足立区としては自己の答弁を裏付ける資料が作成でき、EBPMの取り組みの一環で今後の予算編成の材料にもなりうるため、双方にとっても必要な資料となる。予防接種法第3条「予防接種に関する基本的な計画」の「予防接種の有効性の評価に資する感染症発生動向調査の実施への協力」という役割を果たすことができるのではないか。
(※4)2024年10月11日厚生委員会衛生部長答弁「私個人としては、たくさんの方がこのワクチンを打つことによって死を免れていて、命が助かっている方もたくさんいらっしゃると思います」、2025年1月20日厚生委員会衛生部長答弁「区としては、やはりワクチンを打ったことで救われた人数はかなりいらっしゃるというふうに考えております」。
4.他の多くの自治体の公開事例
陳情者が同じ内容(接種歴・死亡日照合データ)で情報開示請求して、実際に開示した自治体(部分開示や情報提供での公開含む)を以下に示す。
北海道札幌市、東京都(中野区・江戸川区・荒川区・文京区・豊島区・台東区・墨田区・千代田区・中央区・大田区・港区・新宿区・杉並区・目黒区・江東区・北区・町田市・八王子市・福生市・羽村市)、静岡県浜松市、愛知県あま市。
これだけ多くの自治体が公開している中、公開しないことは情報格差を生み、行政サービスの格差を助長することになりはしないか。予防接種法第3条「予防接種に関する基本的な計画」の「住民への情報提供等を行う」中で自治体に情報格差があることは、その役割を全うできていない証左になるのではないか。住民の健康(命)に関わる情報公開に消極的な姿勢は、地方自治法第1条の2「住民の福祉の増進を図る」という理念にそぐわないのではないか。照合の費用については、人口規模が足立区以上の自治体(北海道札幌市・静岡県浜松市)に確認したところ、通常の開示請求業務・情報提供業務の範囲内の対応で、照合用の予算や追加費用は特にないとのことであったので、新たな予算編成等の問題は発生しないと予想される。
以上の理由から新型コロナワクチン接種歴と死亡届の照合データ公開を求めるものである。追加予算の可能性は低く多くの自治体が公開している中で、仮に継続審査が長引けば薬害再発防止を阻害する、遅延させる行為にとられかねない。住民の命を軽んじない賢明な判断を望む。
【下記添付資料略】
(添付資料1)全国死亡者数と2017中位推計(厚生労働省人口動態統計、国立社会保障・人口問題研究所ホームページより)
(添付資料2)足立区死亡者数(東京都保健医療局人口動態統計より)
(添付資料3)全国予防接種健康被害救済制度認定件数(厚生労働省ホームページより)
(添付資料4)足立区予防接種健康被害救済制度認定件数(情報開示請求資料より)
(添付資料5)浜松市2021年2月〜2024年6月までの全死亡者のうち、新型コロナワクチン接種当日・翌日の死亡事例と副反応疑い報告の現状(情報開示請求資料より)
(添付資料6)足立区新型コロナワクチン予防接種健康被害救済制度認定一覧と副反応疑い報告制度との一致(情報開示請求資料より)
(添付資料7)厚生労働省から各自治体へ副反応疑い報告制度周知依頼の通達(PMDA独立行政法人医薬品医療機器総合機構、厚生労働省ホームページより)
(添付資料8)令和5年度厚生労働省所管一般会計歳出予算補正(第1号)各目明細書(資料8ページ目、厚生労働省ホームページより)
(添付資料9)救済制度に関する認知度調査(PMDAホームページより)