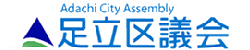
28 補聴器購入助成制度の創設を求める陳情
平成29年11月13日
【陳情の趣旨】
障害の認否に関係なく、聴こえに不自由を感じる誰もが、聴こえを補い安心して暮らせるよう、他の区でも実施している補聴器購入助成の制度を創設してください。
【陳情の理由】
現在区内の難聴者の数は2,193人と伺っております。これは手帳を交付されている人の数と思われますが、高齢期難聴者の数は、おそらくその3〜4倍に達すると思われます。
高齢期難聴者は、聴き分けが難しい(聴き間違いが多い)、耳鳴りを伴うケースも多いなどはあるものの、音としては認識できるので、単純な検査音で示される70デシベルという障害認定基準の数値に及ばない「健聴者」とみなされています。
難聴者の多くが、聴こえづらさ、聴き間違い、何度も聞き返すなどで、会話についていけないため、人と話すことから遠ざかり引きこもったり、家族の会話にさえ加われずにぽつんと取り残されたりしているのです。そればかりか、気配を察知できないために、車や自転車、人などの接近(特に後方)、水道やガスなど生活音にも気付けないなどで、健聴者の方たちには予測もつかない危険やトラブルと常に隣り合わせて暮らしているのが現状です。ですから「社会の一員として、当たり前の人間関係のもとで明るく元気に、安全に暮らしたい」と願う難聴者にとって、補聴器は生活上欠かせないものです。しかしその補聴器は高価で簡単には買えません。
高齢期難聴者の聴こえづらさの程度や幅、種類は多様です。年数をかけて少しずつ聞こえなくなった風や鳥の声、水の音、ざわめき等々が補聴器をつけることで一度にまとめてわっと耳に入ってくるわけですから、単純に大きく聞こえるだけでは疲れるばかりか頭痛や耳鳴りを起こす一因にもなってしまいます。眼鏡で言えば、単純な老眼ではなく乱視や遠視があわさるような症状もあるように、聴こえづらさの程度や種類にも差異があり、それらに適合しない補聴器では、度の合わない眼鏡を使うようなものなのです。それらを勘案すると、聴こえづらさの種類に対応して調整が可能な幅を持った補聴器(最低でも10万円以上はします)が求められるのです。
障害の認否に関係なく、聴こえに不自由を感じる誰もが、聴こえを補い安心して暮らせるよう、他の区でも実施している補聴器購入助成の制度を創設してください。