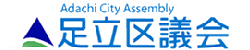
9 選択的夫婦別姓制度の法制化に賛成する意見書の提出に関する陳情
令和元年6月21日
【陳情の趣旨】
議会より国及び関係諸機関に選択的夫婦別姓に賛成する意見書の提出を要望する。
【陳情の理由】
1996年2月26日に法制審議会が民法改正を答申してから23年が経過した。未だ選択的夫婦別姓制度を導入する法改正の見通しは立っていない。最高裁は2015年12月16日に、民法750条「夫婦が、婚姻に際し定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」の夫婦同姓強制規定を合憲と判断した上で、民法の見直しを国会に委ねたが、全く議論が進まないまま今日に至る。
家族の多様化が進む中、日本人同士の婚姻時にのみ夫婦同姓を強要する現行民法は実情にそぐわなくなっており、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップルも少なくない。さまざまな統計をみると、選択的夫婦別姓制度に賛成する人は着実に増加している。
陳情者の妻は、両親の離婚を経験し、改姓手続きの煩わしさをよく知る。そのため陳情者は、結婚の際は、妻側の姓を名乗ることを選択した。しかし、夫である陳情者の両親からは「家を継ぐ気がない」「結婚は家族全員が祝福するものであり、祝福できない」「すぐに元の姓に戻しなさい」と2年以上言われ続け、心療内科にてカウンセリングを受けるほどに、人間関係が悪化している。選択的夫婦別姓制度があれば、妻は妻の、夫は夫の姓を名乗り続けることができたはずである。
また、姓を変更した側から検討すると、結婚後の専門学校・大学・大学院等への出願時に、最終学歴の卒業証明書を旧姓で発行せねばならぬため、旧姓と新姓とが同一人物である証明を、都度用意しなければならず、これが姓を変えることの多い女性のスキルアップを妨げる一つの要因ではないかと感じることもある。住民票やマイナンバーカードにより旧姓を表示できるようになってきてはいるが、銀行口座・証券口座・運転免許証等、名義変更が必要であることは変わらない。
最高裁判決は、民法上は夫か妻の氏どちらかを選ぶことが可能であるから、男女平等であるとする。しかし、戦後の民法改正でイエ制度が廃止されてから70年以上が経過したも関わらず、96%の女性が夫の氏に改姓する現状は、果たして当事者たちの自由意志による選択の結果と言い切れるであろうか。そこに社会的な無言の圧力がないと言えるか。実際、足立区へ婚姻届を出す際に「妻側の姓となっていますが、よろしいのですか」と確認をされたほどである。陳情者の父は「社会とはそういうものだ」と主張する。
また、2015年の最高裁判決では、旧姓使用により改姓の不利益はある程度緩和できるとされたが、旧姓を使用できる企業の数は、内閣府の調査によると未だ半分以下である。法的に保証されない通称(旧姓)は、それを許容するか否かが、勤務先等、相手次第ということになる。個人の呼称として大きな欠陥がある上、必ず使い分けの煩雑さが発生する。管理コストの増大も問題となる。幸運なことに、陳情者の会社では、結婚後も旧姓を使用することが受け入れられているため、会社内での立場は変化していない。このような傾向は多くの会社に広まるべきである。
果たして、姓が異なれば絆の壊れた家族なのだろうか。そもそも家族とは、同姓によってのみ保たれるものではなく、円満な共同生活を送ること、離れていても温かな交流が続くことこそがその基盤となるのではないか。
我が国では、既に個人の権利と平等を求める「女性差別撤廃条約」、「子どもの権利条約」を批准しており、女性の社会的進出、少子高齢化社会が進む中、男女差別、性別役割分業をなくす社会的要請がある。婚姻に際し、一方がその氏を使用できなくなることは、その者の社会生活にとってだけでなく、少子高齢化社会を迎えた日本において、婚姻の減少を招く極めて大きな制約となっていることは明らかである。
昨年1月には、改姓した男性から戸籍法の欠缺を争点とした新たな選択的夫婦別姓訴訟が提起された。通常国会では野党から選択的夫婦別姓に関する質問がされ、当時の野田聖子総務大臣から前向きな答弁がなされるなど、国民の関心と機運は高まっている。
ついては足立区議会より、国及び関係諸機関に対して選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する意見書を提出することを求める。
本件の推進は、「協創力でつくる 活力にあふれ 進化し続ける ひと・まち足立」の振興と発展に大きく貢献するであろう。他の地域に先駆けて家族の多様性を後押しする意見書を提出することで、多様性を認め合い、夢や希望に挑戦する人を増やすことができると思われる。
2019年6月19日には、東京都議会において、選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書の提出に関する請願が、賛成多数で可決された。今年3月の三重県議会での意見書可決に続き、都道府県議会レベルでは2例目である。
選択的夫婦別姓制度は国民がその実現を待ち望んでいたものである。多くの議員の賛同を得て早急に成立するよう、強く求める。