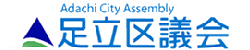
17 花畑運河の歴史文化的価値の保存を求める陳情
令和元年9月10日
【陳情の趣旨】
花畑運河は、荒川放水路の開削に合わせ、綾瀬川と中川を結び舟運の便を図ることを目的として、昭和6年に東京府によって開削された幅約33mの運河です。
以来、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京府を含む関東南部地域全域の舟運の大動脈として、戦前戦後を通じ昭和の成長期の物流を支えてきました。
平成13年、周辺住民の要望により「花畑川を考える会」が組織され、足立区は「平成13年度水辺のレクリエーション施設の整備検討事業計画」に基づき 「身近な自然としての運河、暮らしの中の運河、コミュニティの核としての運河」をコンセプトとして「平成13年度花畑川環境整備基本計画」をまとめ、これまで周辺住民に計画の実施を周知してきました。
足立区景観条例(平成21年)に準拠して作成した「足立区景観計画の方針」においても「花畑川を景観の軸」と定めています。花畑川の標準33.31mの水面幅について、足立区景観計画には「花畑川は適度な川幅を有し市街地に近接しているため、身近な水辺空間として、地域の住民に親しまれています。」と記載しています。
しかし、平成13年度策定のこの計画と現在事業実施を進めている「令和元年7月30日地元説明の花畑川環境整備事業計画」は、あまりにもその内容において異なるものとなっており、「運河の保存」というコンセプトが失われてしまいました。ところが、令和元年案の地元説明では、「平成13年度案を継承している」と住民に説明しており、誤解を与えかねません。さらに、故意に設計諸元の数字を記載しなかったり、平成13年度案で22.78mの河川幅員計画を20mと記載したりして説明をしています。
そこで令和元年8月21日、近藤やよい区長へ内容証明便にて質問をしたところ、9月2日に回答書が届きましたが、これまで継承していると住民に説明してきた「平成13年度花畑川環境整備基本計画」を完全に否定する見解をいただき、驚愕したところです。
回答書では、足立区道路整備室工事課から「花畑川を文化財とは考えておりません」との見解をいただきました。花畑川の貴重な文化的価値は、大正から昭和にかけて日本の近代化に大きな役割を担った、荒川放水路開削に密接に関連しており、舟運の混雑緩和のために開削された運河という90年近い歴史にあるのです。その後の時代を経ても約33mという広い水面幅を維持していることは、舟運が盛んな時代を偲ばせるもので、まさに日本の宝といえる文化財です。
現在では往時の舟運の賑わいはありませんが、東京の三十間堀川や築地川など、この時期に建設された多くの運河や堀が埋められ消滅している中で、建設当時の形態をそのまま残す、貴重な近代土木遺産とも言うべき存在となっています。また、21世紀を迎えた現在では、舟運の良さが再評価され、河川、水路、運河での舟運の再興が全国各地で企画、実施されています。東京都内においても日本橋を中心とする遊覧船観光や、羽田空港から都心への旅客輸送、晴海オリンピック選手村後のニュータウンの通学・通勤輸送や、災害時の救援物資輸送などの計画が進んでいます。墨田区の北十間川、江東区の小名木川、江戸川区の新川、草加市の綾瀬川などでの和船遊覧、品川区、大田区などでの屋形船などがますます盛んになっています。このような時に、33mという広い水面を4.5〜17mに縮めてしまう現在の計画は、花畑川の価値を失うことになり、次世代に対し将来の発展やにぎわいの可能性を閉ざすことにもなり、禍根を残す判断ではないでしょうか。
さらに、回答書において「花畑川は準用河川であり(中略)、地域住民と足立区の財産と考えております」また花畑川は「道路整備室工事課が管理責任者です」との見解をいただきました。
しかし、準用河川とは大規模な河川工事が予定されておらず行為規制や維持工事によって対応が可能な河川について、管理を市町村長(この度は足立区長)に地方自治法の法定受託事務として位置付けされているものです。管理の内容は、河川法に準じて行われるとされており、法に基づき河川の敷地は国有地とされております。河川法の適用を受けない普通河川の敷地が、市町村有とされていることとは根本的に異なります。花畑川は東京都から足立区へ無償譲渡されたものではなく、公物としての管理を委任されたものです。
また、これまで花畑運河の開削や堤防護岸の建設には、国費や都費(府費)が投入された人工公物であり、長年にわたり東京都が管理してきました。このような歴史的経緯を鑑みますと道路整備室工事課が言われる「花畑川は準用河川であり(中略)地域住民と足立区の財産と考えております」という見解は、準用河川の法的解釈を誤解されているとしか思えません。
さらに「道路整備室工事課が管理責任者である」との回答ですが、土地の占用や工事の許可事務も道路整備室工事課が管理者と断言することは、河川法の求める管理委任の考え方を大きく逸脱しています。さらに足立区事務分掌の定めでも道路整備室工事課に河川管理者の権限を委ねていません。そこで工事に当たっては河川管理者としての「足立区長」による工事許可、占用許可などの手続きが必要です。準用河川といえども河川法の適用を受けているので、河川管理者は足立区長です。同時に道路工事者としての「足立区長」と、河川管理者としての「足立区長」との間の協議、占用許可手続きも必要であり、これは「道路整備室工事課」が所掌権限として兼務できない行政行為です。
また「現護岸のコンクリート部分を低木植栽にし、堤防上に桜を連続して植えることから、緑の基本計画に抵触しておりません」との回答ですが、現護岸のコンクリート部分に植栽するだけというならば、現況の法尻から法尻の河床幅28.17mは確保しているというお答えにもみえます。それならば17mまで埋め立てる必要はないのではないかと思慮します。
回答欄に「歴史・文化・環境破壊につながる事業展開を行なっていないため、専門委員会を設置する予定はございません」とありますが、これまでに述べた諸所の観点からも、専門委員会の設置は必須であると考えます。そこで、以下の事項を求めます。
【陳情項目】
1.河川法の趣旨に基づき事業計画を作成し、河川法に基づく手続きを行い、河川法を遵守した事業を実施すること。
2.花畑川の関東利根川流域と荒川流域を結んできた舟運の大動脈である歴史文化性を鑑みた、「平成13年度花畑川環境整備基本計画」の事業を推進すること。
3.花畑川の幅は、平成13年度花畑川環境整備基本計画のとおり最低約23mの水面幅を確保すること。
4.将来にわたって、花畑川の運河としての舟運を可能とし、災害緊急時の人的・物的輸送にも資するため、現在の中川、綾瀬川の水門を存続し、現行の水門幅を残すこと。
5.足立区景観計画を遵守した事業とすること。
6.花畑川運河の歴史文化的価値を保存するために、設計に当たっては、足立区郷土史家や土木学会歴史委員会委員、多自然川づくりアドバイザー、日本河川協会などを加えた専門委員会を設置して検討すること。