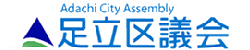
1丂抧堟堛椕傪庣傞偨傔偵丄2024擭搙恌椕曬廣夵掕偺嵞専摙傪媮傔傞堄尒彂傪崙偵採弌偡傞偙偲傪媮傔傞捖忣
椷榓6擭6寧5擔
亂捖忣偺庯巪亃
丂抧堟堛椕傪庣傞偨傔偵慡偰偺堛椕廬帠幰偺張嬾偑夵慞偝傟丄埨掕揑偵恖嵽妋曐偑壜擻偲側傞曽岦偵夵掕偝傟傞傛偆丄崙偵懳偟偰2024擭搙恌椕曬廣夵掕偺嵞専摙傪梫媮偟偰偔偩偝偄丅
亂捖忣偺棟桼亃
丂偼偠傔偵丄2024擭搙恌椕曬廣夵掕偵偮偄偰偼丄埲壓偺栤戣揰傪書偊傞夵掕偱偁傝傑偡丅
1丏抧堟堛椕傪巟偊傞拞彫婯柾偺堛椕婡娭偑戝暆尭廂偱宱塩崲擄偵娮傞偙偲偵傛傝抧堟堛椕偺曵夡傪彽偔
2丏帠嬈強丒怑庬娫偱晄岞暯偲暘抐傪惗傓儀乕僗傾僢僾昡壙椏偼埨掕偟偨堛椕採嫙懱惂偺妋曐偵塭嬁
3丏枬惈幘姵娗棟偺3幘姵彍奜偼丄挿婜張曽傗堛椕DX偺悇恑偵傛傝姵幰偺庴恌梷惂偑恑傒寬峃娗棟偑屻戅
4丏儅僀僫曐尟徹偺妶梡傪栚揑偲偟偨堛椕DX偺悇恑偼丄曐尟徹偺攑巭偩偗偱側偔姵幰忣曬偺娗棟偵傕栤戣
丂恌椕曬廣偼崙柉奆曐尟偺壓偱丄崙柉偑庴偗摼傞堛椕偺幙偲検丄曽朄傪曐忈偡傞傕偺偱偡丅堛椕婡娭偺宱塩偲恌椕婡擻偺堐帩傪曐忈偡傞傕偺偱偁傞偙偲偼傕偪傠傫丄偦偺偙偲傪捠偠偰崙柉偵懳偡傞椙幙側堛椕傪採嫙偡傞尨帒偵側傝傑偡丅崙柉奆曐尟惂搙偼丄幮夛曐忈偺堦娐偲偟偰丄寷朄25忦偵婎偯偔傕偺偱偁傝丄崙柉奆曐尟惂搙偺塣塩庡懱偱偁傞崙偼丄帪乆偺忣惃偵墳偠偰丄曐尟堛椕婡娭偺宱塩傪埨掕偝偣丄崙柉傊偺堛椕採嫙懱惂傪曐忈偡傞愑擟偑偁傝傑偡丅崙偼丄挿擭偺掅堛椕旓惌嶔偺壓丄僐儘僫壭傗暔壙崅摣偱旀暰偟偨堛椕採嫙傪棫偰捈偡偨傔偵丄恌椕曬廣傪戝暆偵堷偒忋偘傞傋偒偱偡丅
丂戞24夞堛椕宱嵪幚懺挷嵏偐傜傕丄堛壢恌椕強乮堛椕朄恖乯偺堛嬈棙塿棪乮僐儘僫曗彆嬥娷傑偢乯偵偮偄偰丄枹慮桳偺僐儘僫姶愼奼戝偺拞丄恌椕強偑丄媥擔栭娫曉忋側偳偱抧堟堛椕偵暠摤偟偰傕丄僐儘僫捈慜偺宱塩悈弨乮2019擭搙丗6.5亾乯偲傎傏曄傢偭偰偄側偄偺偑尰忬偱偡丅傑偨丄僐儘僫庴擖偵暠摤偟偨摿偵柉娫昦堾偺堛嬈棙塿棪傕丄僐儘僫曗彆嬥傪彍偔偲偨偪傑偪戝暆側愒塅乮2022擭搙丗亅1.3亾乯偵揮姺偟偰偄傑偡丅偙傟偼丄2023擭搙懪偪愗傜傟偨僐儘僫曗彆嬥婯柾偺恌椕曬廣夵掕偺堷偒忋偘偑柍偄偲宱塩傪堐帩偱偒側偄堎忢側帠懺偱偡丅
丂傑偨丄堛椕娭學怑庬乮堛巘丒帟壢堛巘丒栻嵻巘丒娕岇巘傪彍偔乯偺寧媼梌暯嬒偼32.7枩墌偲慡嶻嬈暯嬒36.1枩墌傪10亾嬤偔壓夞偭偰偄傑偡丅捓忋偘偵娭偡傞恌椕曬廣夵掕偼丄帠嬈強偛偲丄摨偠怑庬娫偱捓忋偘妟偑曄傢傝丄捓忋偘懳徾奜偺怑庬傕偄傞偙偲偐傜怑堳娫偺暘抐傪偆傓偩偗偱側偔怑堳妋曐偲堛椕採嫙懱惂偺堐帩偵塭嬁偑弌傞偙偲偼柧傜偐偱偡丅
丂偦偺傛偆側拞丄夵掕棪偺撪栿偼丄娕岇怑堳丒昦堾栻嵻巘側偳偺廬帠幰偺捓忋偘偱0.61亾丄擖堾偺怘帠椕梴旓0.06亾丄偦偺懠偱0.46亾乮堛壢0.52亾丄帟壢0.57亾丄挷嵻0.16亾乯偺堷偒忋偘偲側傞偑丄惗妶廗姷昦傪拞怱偲偟偨娗棟椏丄張曽獬椏摍偺嵞曇摍偺岠棪壔丒揔惓壔偱0.25亾偺堷偒壓偘偑惙傝崬傑傟丄恌椕曬廣杮懱偺夵掕棪偼僾儔僗0.88亾乮崙旓儀乕僗偱栺800壄墌乯偲側傝傑偟偨丅偟偐偟丄捓忋偘偺堷偒忋偘暘偼丄恖審旓偱慡偰巊梡偡傞偨傔丄杮懱夵掕棪偼幚幙儅僀僫僗偲側傝傑偡丅峏偵丄栻壙偲嵽椏偱1.OO亾乮栻壙0.97亾丄嵽椏壙奿0.02亾乯偑堷偒壓偘傜傟丄僩乕僞儖偱偼6夞楢懕偺戝暆側儅僀僫僗夵掕偱偡丅
丂傑偨丄廳揰崁栚偲偟偰偼埲壓偺偲偍傝偱偡丅
1丏擖堾
廳徢搙丄堛椕丒娕岇昁梫搙偼媫惈婜偺姵幰偵偳偺掱搙偺娕岇傪採嫙偟偰偄傞偐傪昡壙偡傞偨傔偺巜昗偱偁傞丅偮傑傝丄偙偺昦堾偱偼偳傟偩偗偺娕岇巘傪昁梫偲偟偰偄傞偺偐傪昡壙偡傞巜昗偱偁傞丅崱夞偺夵掕偱偼丄娕岇懱惂偑庤岤偄媫惈婜昦搹偺巜昗偐傜娕岇偑峴偆働傾偺昡壙偑嶍彍偝傟偨丅傑偨丄偦偺懠偺崁栚偱傕崅楊幰偵懡偄撪壢宯幘姵偱偼昡壙偑掅偔側傝丄掅偄曬廣偵側傞傛偆曄峏偝傟偰偄傞丅宱塩揑側懁柺傪廳帇偡傞偲丄崅楊幰偑媫惈婜昦搹偐傜捛偄弌偝傟傞偙偲偵側傝偐偹側偄丅崅楊幰媬媫偺庴偗嶮偲偟偰崙偑憐掕偟偰偄傞昦搹偱偼堦斒姵幰偺媬媫傛傝傕庤敄側娕岇懱惂偲側傝丄梕懺偑媫曄偟傗偡偔丄廳徢壔儕僗僋傕崅偔丄傛傝庤岤偄娕岇働傾偑昁梫側崅楊幰媬媫傪寉帇偟偰偄傞丅
2丏撪壢巜摫椏乮奜棃乯
崱夵掕偱偼丄崅寣埑丒崅帀寣徢丒摐擜昦偺3幘姵偑丄怴愝偺巜摫椏乮惗妶廗姷昦娗棟椏嘦乯偵堏峴偡傞丅3幘姵偼撪壢姵幰偺7妱埲忋傪愯傔傞偲梊憐偝傟丄嶼掕偟側偗傟偽10乣20亾偺尭廂偵側傞偨傔懳墳偣偞傞傪摼側偄偑丄嶼掕梫審偲偟偰姵幰偛偲偺寁夋彂岎晅偑媮傔傜傟丄堛巘拞怱偵朿戝側幚柋偑敪惗偡傞丅傑偨丄懸偪帪娫偺憹壛傗寁夋彂傊偺彁柤傪媮傔傞偙偲偱丄挿擭攟偭偰偒偨姵幰偲偺怣棅娭學傪朩偘傞偙偲偑寽擮偝傟傞丅
3丏儕僼傿儖張曽獬丒挿婜張曽乮奜棃丒嵼戭乯
僐儘僫壭偱丄揹榖偵傛傞張曽獬敪峴傗寬峃恌抐偺枹庴恌側偳偑挿婜壔偟偨寢壥丄昦忬埆壔傗偑傫敪徢偑憹壛偟偨丅掕婜捠堾偵傛傞枬惈幘姵娗棟丄拞抐姵幰攃埇偼廳梫偩偑丄儕僼傿儖張曽獬丄挿婜張曽偺悇彠偼丄姵幰傪庴恌婡夛偐傜墦偞偗丄昦忬埆壔傪堷偒婲偙偟堛椕偺幙偺掅壓丄堷偄偰偼堛椕旓偺憹戝傪彽偔偙偲偵偮側偑傞丅
4丏儅僀僫曐尟徹丒堛椕DX乮擖堾丒奜棃丒嵼戭嫟捠乯
摉僌儖乕僾偺儅僀僫曐尟徹棙梡棪偼3亾掱搙偩偑丄廂塿傪妋曐偡傞偨傔偵偼儅僀僫曐尟徹傪悇恑偡傞懱惂傪惍旛偟偨傝丄崙偵姵幰忣曬傪僨乕僞偱採弌偡傞偙偲偱壛嶼傪庢傜偞傞傪摼側偄撪梕偲側偭偰偄傞丅僨乕僞採弌偺幚柋偼暋嶨丒朿戝偱偁傝丄傑偨丄杮棃堛椕婡娭偲姵幰偺傕偺偱偁傞恌椕忣曬傪崙偵採弌偣偞傞傪摼偢丄庣旈媊柋偺宍奫壔偵傕偮側偑傞丅崅楊幰傗忈偑偄幰摍乽僨僕僞儖庛幰乿偺堛椕偦偺傕偺傊偺傾僋僙僗偺朩偘偵側傞嫲傟偑偁傞丅
5丏堛椕DX摫擖偺栤戣揰
條乆側棙曋惈偑岦忋偡傞偲鎼傢傟偰偄傞偑丄堦曽偱忣曬楻塳傗僴僢僉儞僌儕僗僋摍偺僙僉儏儕僥傿偺栤戣傗價僢僋僨乕僞偲偟偰姵幰偺忣曬傪崙偑攃埇偡傞偙偲偱丄屄恖忣曬丒僾儔僀僶僔乕偺怤奞偵側傝摼傞偙偲丄傑偨崅楊幰傗忈偑偄幰側偳偺僨僕僞儖壔偑晄姷傟側曽乆傊偺僨僕僞儖奿嵎偑寽擮偝傟傞丅峏偵僨僕僞儖僣乕儖傪摫擖偡傞偨傔丄僔僗僥儉偺僩儔僽儖傗傾僢僾僌儗乕僪丄儊儞僥僫儞僗摍偺嶌嬈傗旓梡偑敪惗偟丄堛椕婡娭偺宱塩傪埑敆偡傞偙偲偑梊憐偝傟傞丅
丂岞揑堛椕婡娭偑側偄懌棫嬫偱抧堟堛椕傪巟偊偰偄傞柉娫偺拞彫堛椕婡娭偑宱塩崲擄偵娮傟偽丄抧堟堛椕偼曵夡偟傑偡丅抧堟堛椕傪庣傞偨傔偵丄崙偵懳偟偰2024擭搙恌椕曬廣夵掕偺嵞専摙傪梫媮偟偰偔偩偝偄丅